Contents
エコー検査、医師と臨床検査技師で迷っていませんか?
エコー検査は医師か?臨床検査技師か?というテーマに、
戸惑いや疑問を感じているあなたへ。
「これって医師がやるべき?臨床検査技師に任せる?」
「指示はするけど、自分で描出できないのが不安」
そんなふうに悩んだことはありませんか?
実際、エコー検査の役割には、
明確な線引きがありそうで、現場によってバラつきも。
この記事では、それぞれの役割と、
両者がどう連携することで診療の質を高められるかを解説します。
医師と臨床検査技師、それぞれの役割の基本
一般的に、
・エコー検査の実施(描出)→臨床検査技師
・エコー所見の読影・診断→医師
という役割分担が多く見られます。
ただし、これはあくまで“よくある体制”。
医師が自ら描出を行う診療所や、
臨床検査技師が深く問診・診察内容を把握している現場も存在します。
つまり、エコー検査における医師と技師の関係は、
「役割分担」ではなく「共同作業」と捉える方が自然です。
それぞれの強みを活かすことで診療はもっと良くなる
技師は描出のプロフェッショナル。
解剖・プローブ操作の知識を持ち、
限られた時間で見逃さない技術に長けています。
一方で医師は、
問診や身体所見など総合的な診察を踏まえた上で、
臨床判断・治療方針を決定する役割を持ちます。
ここで、エコー検査において
医師と臨床検査技師という立場を越えて、
双方が画像の“意図”を共有しながら使うことで、
診療はより精度の高いものになります。
「技師任せ」がリスクになるケースも
すべて技師に任せてしまうと、
「医師の意図」と「技師の描出」がズレることがあります。
たとえば腹部エコーで、
医師は「膵臓を丁寧に見てほしい」と思っていても、
技師が“ルーチンの描出”だけで終えてしまうと、
必要な病変を見落とすリスクも。
だからこそ、医師、技師それぞれが、
お互いの立場を理解し、目的を共有することが重要です。
では、医師は描出スキルを持つべきか?
結論から言えば、
最低限の描出スキルは“持っておいた方が良い”です。
特に緊急時や外来で、
「今すぐ診たい」という場面では、
自らエコーを使えれば対応力が格段に上がります。
また、医師が少しでも描出の流れを理解していれば、
技師との連携もスムーズになります。
「どの描出が難しいのか」「何を観察すべきか」を
会話できるようになるからです。
SASHIでは医師も技師も描出力を高められる
描出スキルを効率よく身につけたいなら、
実践的なトレーニングが欠かせません。
SASHIの研修では、
・オーダーメイドの指導
・実際の診療シーンを想定した描出練習
・プロ講師によるフィードバック
を通じて、
現場で即使える技術を習得できます。
医師向け・技師向けに分かれた指導も可能で、
「チームとしてスキルを底上げしたい」という
医療機関からの依頼も増えています。
まとめ|“協働”でこそエコーは活きる
エコー検査を医師と技師という視点で見たとき、
一方が主導して他方が従う、という構図はもう古いかもしれません。
これからは“協働”と“相互理解”がキーワード。
・役割を知る
・強みを活かす
・学び合う姿勢を持つ
この3つが揃えば、
あなたの診療も、患者の安心も、
きっとワンランク上に進化します。
「任せるだけ」から「一緒に診る」へ。
その一歩を、ぜひSASHIで踏み出してください。
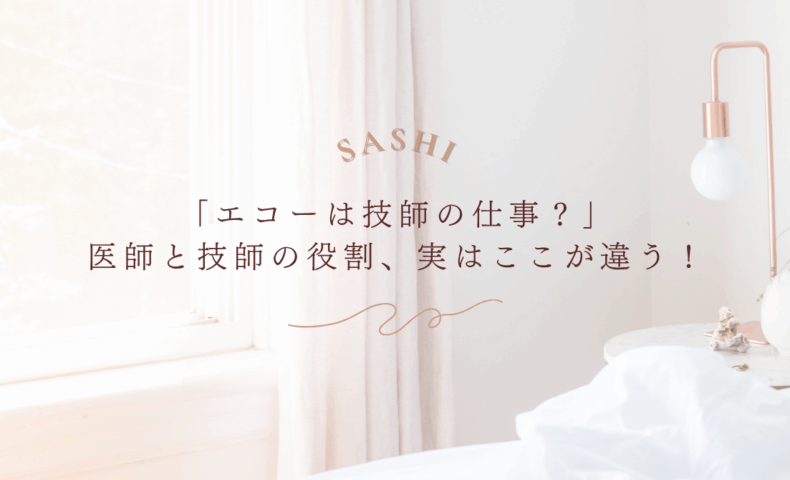







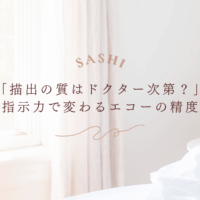
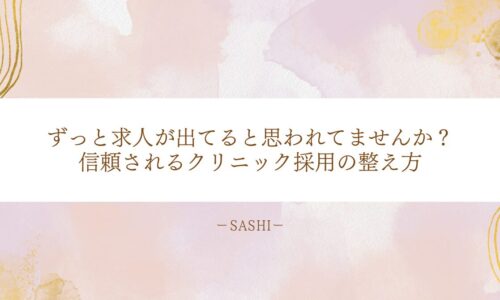
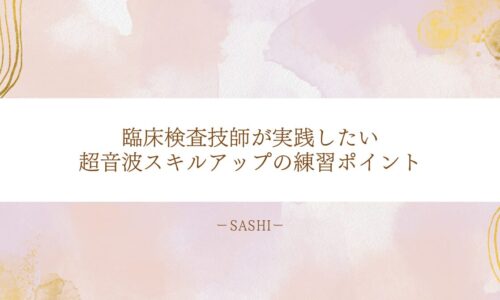

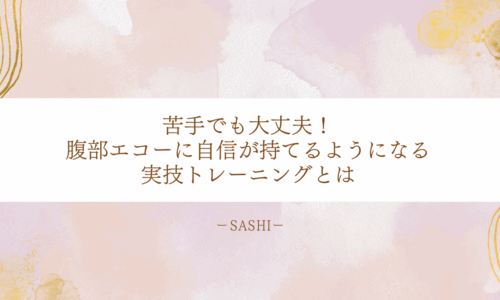

この記事へのコメントはありません。