Contents
技師に任せきりでいい?エコー検査に悩む医師のあなたへ
「うまく描出してもらえない…」
「所見がしっくりこない…」
そんな経験はありませんか?
その原因、もしかすると“医師の指示力”にあるかもしれません。
何を見たいのか、どこを疑っているのか。
それが明確でなければ、技師も最適な描出はできません。
この記事では、エコー検査の精度を高めるために、
医師側ができる工夫と考え方をお伝えします。
エコーは「撮る」だけでなく「診る」検査
「技師が撮った画像を読むだけ」では、質の高い診断はできません。
エコーはリアルタイムかつ動的な検査。
医師の診たいポイントと技師の描出意図が噛み合わなければ、
得られる情報の質は下がってしまいます。
だからこそ、医師自身が「描出の設計図」を持つことが大切です。
たとえば、
「この症状があるので肝周囲を重点的に」
「腫瘤が疑われるので、ドプラで血流も確認して」
など、目的を明示するだけで、
検査の価値は格段に高まります。
指示力を上げる3つのコツ
1. 背景情報を簡潔に共有する
エコー前に、主訴や経過、気になる疾患を一言添えるだけで、
描出の方向性がクリアになります。
2. 撮影後のフィードバックを忘れずに
「このカットは助かりました」
「次はここも加えてほしい」
といったやり取りがあると、
技師との信頼関係が深まり、検査の質も向上します。
3. リアルタイムで一緒に確認する
検査中に画面を一緒に見ることで、
「もう少し右」「この構造は何?」と
即座の修正や新たな気づきが得られます。
こうした対話こそ、エコー診断の醍醐味です。
技師の力を引き出すのも医師の役割
いかに優れた技師がいても、
医師の意図が伝わらなければ、画像は“ただの記録”で終わってしまいます。
逆に、明確な指示があることで、
技師の力が存分に発揮され、検査の精度は格段に上がります。
エコー診断では「任せること」と「放任すること」は違います。
医師の関与が、結果を左右するのです。
SASHIで学べる「伝える力」のトレーニング
SASHIでは、医師向けに“伝える力”を強化する実践研修を提供しています。
- 描出意図の明確な伝え方
- 問診から描出・読影までの流れの整理
- 現場のやり取りを想定したロールプレイ
これらを通じて、技師との連携力と診断精度を同時に高めることが可能です。
「もっと連携がスムーズになれば」
「技師と共に診断精度を高めたい」
そんな思いがある方におすすめの研修です。
描出の質は「指示力」で変えられる
エコー検査の質は、医師の関与によって大きく変わります。
- 目的を共有する
- リアルタイムで確認する
- 結果に基づいてフィードバックする
この3つを実践するだけで、
“見えなかった所見が見える”検査に変わります。
医師だからこそ担える「設計者」としての役割。
その一言が、診断の精度を左右します。
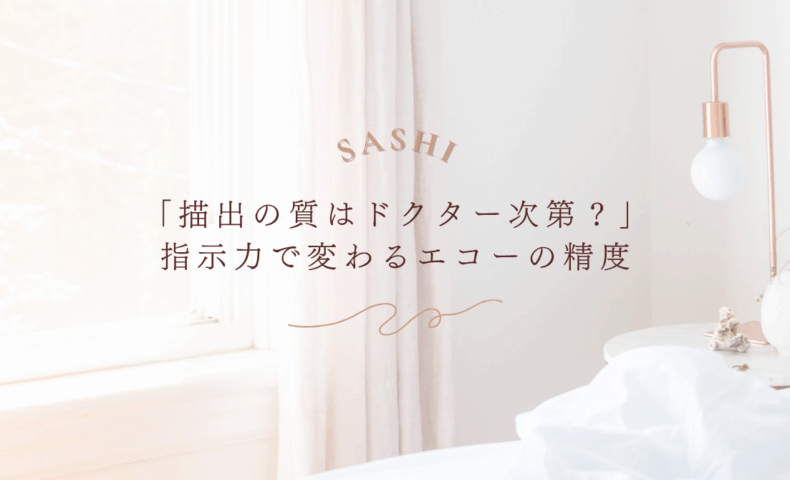
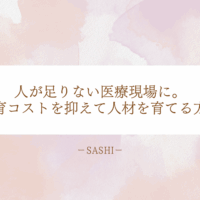






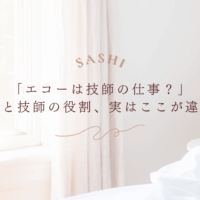
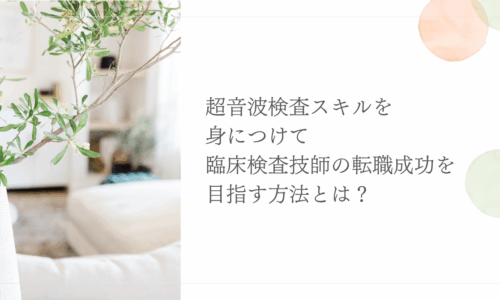
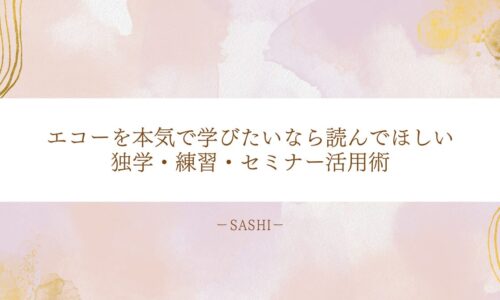



この記事へのコメントはありません。