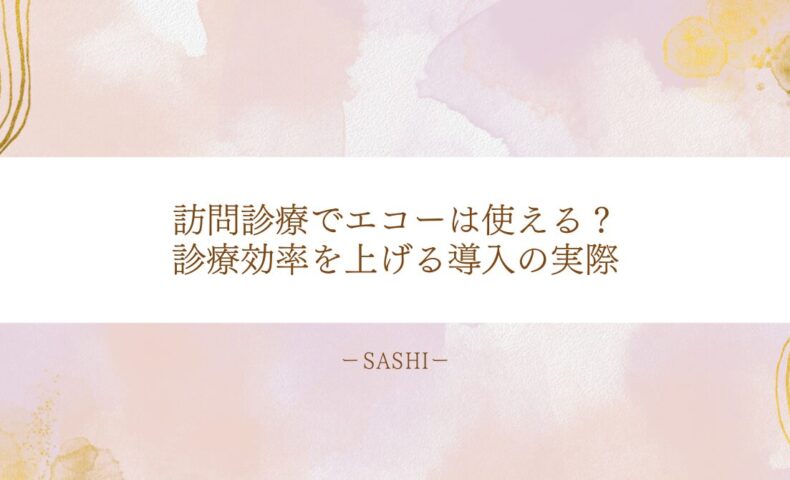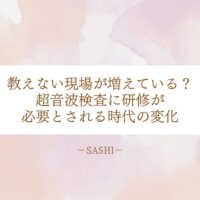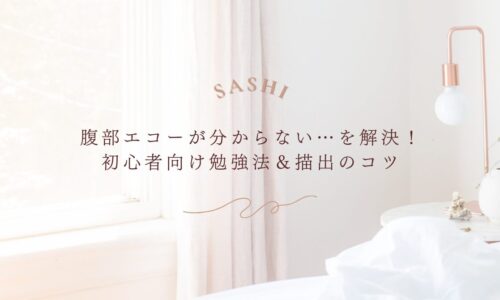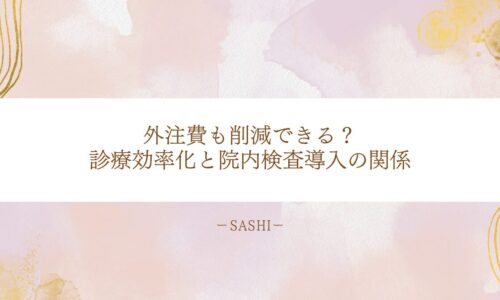「在宅や施設で使いたいけど、うまく活用できるか不安…」
と感じていませんか?
訪問診療のエコー、特にポータブルは持ち運びに便利で、
即時診断が可能になる一方で、
視野が狭いために使いこなすには練習が必要です。
そこでこの記事では、
まず病院などで一般的な据え置き型エコー機でしっかり練習し、
それからポータブルエコーへ移行することで、
訪問診療でのエコーを素早く、
かつ安全に使えるようになる方法をお伝えします。
Contents
SASHIのセミナーを活用するという選択肢
もし、院内での十分な練習環境が確保できない、
あるいは効率的にスキルを習得したいという場合は、
私たちSASHIが提供する
超音波ハンズオンセミナーを活用するのも一つの手です。
SASHIでは、訪問診療を見据えた描出練習、
ポータブル機の操作の練習などを含めた内容が可能であり、
初心者の医者でも安心して
基礎から応用まで学べる体制が整っています。
なぜ訪問診療 エコーで失敗しやすいのか?
ポータブルエコーは持ち運びやすくて直感的ですが、
画面サイズが小さく、視野が狭いために、
どこをどう撮れば良いのか迷いやすいのが難点です。
特に臓器間の位置関係や血流方向など、全体像を把握しづらく、
画像の理解に時間がかかることもあります。
そのため、本当に使いこなすためには練習が不可欠です。
最初に据え置き型エコーで基礎固めを
据え置き型(カート式)エコー機での練習が大切な理由は、
画面が大きく、視野が広いために解像度も高く、
臓器の位置関係もわかりやすいからです。
具体的には:
- 肝臓と胆嚢、腎臓などの臓器間の位置と構造を正確に理解
- モード切替を通じて、血流や動きの理解を深める
- 操作感と機能を繰り返し使い、自然に手が覚える
これにより、どの位置でどの画像が得られるか理解しやすくなり、
ポータブルエコーへの移行がスムーズになります。
ポータブルエコーで使いこなすために
据え置き型で経験を積んだ後、実際にポータブルエコーを使う際は、
以下のポイントを意識しましょう。
- どこを診るか目的を絞る
「胸水」「腹水」「心嚢液」など、見たい部位を明確に。 - 撮影時間を意識して訓練
訪問診療は時間との勝負。限られた画角で集中すると効率が上がります。 - 撮影映像を保存して見直す
先輩医師や検査技師とレビューすると、理解が深まります。
この流れで学べば、「訪問診療にエコーを導入したけれど使いこなせなかった…」
というよくある失敗を防ぐことができます。
診療効率を上げるための練習の流れ
以下のようにステップを踏むと効率的です:
- 病院や研修施設でカート式エコーの練習時間を確保
- 基本的な胸部・腹部・血流描出を習得
- 撮影映像を共有し、フィードバックを得る
- ポータブルエコーに切り替え、短時間で必要なカットを収める訓練
- 定期的な振り返りでスキルを深める
この方法で進めれば、訪問診療でエコーを導入しても
即、実践で役立てられるようになります。
まとめ:訪問診療にエコーの実用化を最短ルートで
訪問診療のエコーは便利ですが、狭視野のために練習なしに使うと
診断ミスや時間ロスにつながります。
だからこそ、まず据え置き型で“描出力と画角感覚”を鍛えてから、
ポータブルエコーへ移行するのが最も効率的で合理的です。
あなたなら、適切なトレーニングで訪問診療に
エコーを自在に使いこなせるようになります。
まずは病院での練習環境を探してみてください。そこから、大きく変わります。